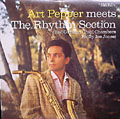 そういう人たちは一様にこの写真を思い浮かべてる筈なのだ。ツイードのジャケットを着て木にもたれ掛かり、物憂げに右斜前方51°を見やる好青年。確かにこの『ミーツ・ザ・リズム・セクション』(196 )がもっともよく知られているアルバムであることには違いないのだが、アート・ペッパーはこれだけじゃない。アート・ペッパーはなかなかハード・ボイルドで名前の通り(ってワケじゃないだろうけど)ぴりっと辛いアルト吹きなのだ。
そういう人たちは一様にこの写真を思い浮かべてる筈なのだ。ツイードのジャケットを着て木にもたれ掛かり、物憂げに右斜前方51°を見やる好青年。確かにこの『ミーツ・ザ・リズム・セクション』(196 )がもっともよく知られているアルバムであることには違いないのだが、アート・ペッパーはこれだけじゃない。アート・ペッパーはなかなかハード・ボイルドで名前の通り(ってワケじゃないだろうけど)ぴりっと辛いアルト吹きなのだ。よくこの人に関しては「引退前と復帰後とどちらがいいか」ということが話題に上る。ジャズメンの中にはよく一時的に演奏活動から遠ざかったり、あるいは遠ざかっているように見えたり(仕事が少なくてレコードの吹き込みがなくなる)する場合が見受けられる。アート・ペッパーは麻薬で捕まったり、いろいろした所為でよく小さな中断はあったのだが(上の『ミーツ〜』もその前はしばらく吹いていなくて楽器が故障したままレコーディングしたそうである)、ホントに完全に演奏活動を止めていた時期がある。その間はアコーディオンのセールスマンかなんかをやっていたのだ。で、ある時レコード会社のプロデューサーか誰かの取りはからいにより奇跡的に復帰を果たす。
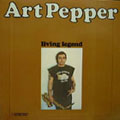 その復帰作というのがこの『Living Legend』(1975)。生ける伝説。というより「刑期満了」とかそんな雰囲気だな、この写真じゃ。それはともかく、ハンプトン・ホーズ(piano)、チャーリー・ヘイデン(bass)、シェリー・マン(drums)というマニアが大喜びする渋いメンバーだ。ペッパー自身もブランクを感じさせないパワフルな演奏を繰り広げる。タイトル曲なんて「どがっ」てな感じに物凄く重厚な存在感のある演奏。そして(追加、5行ほど)
その復帰作というのがこの『Living Legend』(1975)。生ける伝説。というより「刑期満了」とかそんな雰囲気だな、この写真じゃ。それはともかく、ハンプトン・ホーズ(piano)、チャーリー・ヘイデン(bass)、シェリー・マン(drums)というマニアが大喜びする渋いメンバーだ。ペッパー自身もブランクを感じさせないパワフルな演奏を繰り広げる。タイトル曲なんて「どがっ」てな感じに物凄く重厚な存在感のある演奏。そして(追加、5行ほど)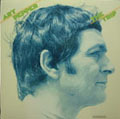 そしてその後の『The Trip』(1976)。文句なくカッコいい。タイトル曲なんてもう泣いちゃうな。「Sweet Love of Mine」なんていう人気曲(ただし日本では有名だけどアメリカ本国ではそうでもないらしい)も取り上げていて楽しめる。ピアノのジョージ・キャブルスはこの後しばしば共演することになる。ドラムスにはエルビン・ジョーンズが入っている。内容には関係ないけどジャケットの写真もジュリアス・シーザーの彫像みたいでいいですね。
そしてその後の『The Trip』(1976)。文句なくカッコいい。タイトル曲なんてもう泣いちゃうな。「Sweet Love of Mine」なんていう人気曲(ただし日本では有名だけどアメリカ本国ではそうでもないらしい)も取り上げていて楽しめる。ピアノのジョージ・キャブルスはこの後しばしば共演することになる。ドラムスにはエルビン・ジョーンズが入っている。内容には関係ないけどジャケットの写真もジュリアス・シーザーの彫像みたいでいいですね。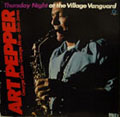 エルビン・ジョーンズとはその後Villege Vanguardでの3日間にわたるライブの録音がある(1977)。4枚組(Thursday〜Saturdayともう一枚)の聴きごたえのあるアルバムだが、演奏の集中度では木曜日が一番だろう(と思わず勢いで書いてしまったが実は金曜日のは入手しそこなって聴いていないのだった)。「Valse Triste」なんてびりびり緊張感が走ってます。笑っちゃうのは(笑っちゃいけないんだろうけど)ペッパーのオリジナル曲「My Friend John」。コーラスの継ぎ目でちょっとした決めのフレーズを入れるんだけど、作曲した本人が小節数を間違えてとんでもないところで入っちゃいそうになってる。まぁ、妙に構成が複雑な曲なので間違えない方が不思議なくらい。でも他のメンバーはちゃんと間違えずにやってるからさらに不思議。
エルビン・ジョーンズとはその後Villege Vanguardでの3日間にわたるライブの録音がある(1977)。4枚組(Thursday〜Saturdayともう一枚)の聴きごたえのあるアルバムだが、演奏の集中度では木曜日が一番だろう(と思わず勢いで書いてしまったが実は金曜日のは入手しそこなって聴いていないのだった)。「Valse Triste」なんてびりびり緊張感が走ってます。笑っちゃうのは(笑っちゃいけないんだろうけど)ペッパーのオリジナル曲「My Friend John」。コーラスの継ぎ目でちょっとした決めのフレーズを入れるんだけど、作曲した本人が小節数を間違えてとんでもないところで入っちゃいそうになってる。まぁ、妙に構成が複雑な曲なので間違えない方が不思議なくらい。でも他のメンバーはちゃんと間違えずにやってるからさらに不思議。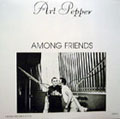 そして昔のヤク仲間?のラス・フリーマン(piano)との再会セッション『Among Friends』(1978)も楽しい。ラス・フリーマンはずっとジャズの世界から足を洗っていて、映画音楽の仕事とかピアノの先生とかをしていたんだそうである。だからジャズの演奏スタイルは1950年代のままである。でもそれがまた楽しい。タイトル曲のオリジナルのブルース以外はみんなよく知られたスタンダードナンバーなので安心して聴ける。企画が日本人なんだよな、これ。ちなみにジャケット写真でペッパーに迫ってる(笑)のはフランク・バトラー(drums)。
そして昔のヤク仲間?のラス・フリーマン(piano)との再会セッション『Among Friends』(1978)も楽しい。ラス・フリーマンはずっとジャズの世界から足を洗っていて、映画音楽の仕事とかピアノの先生とかをしていたんだそうである。だからジャズの演奏スタイルは1950年代のままである。でもそれがまた楽しい。タイトル曲のオリジナルのブルース以外はみんなよく知られたスタンダードナンバーなので安心して聴ける。企画が日本人なんだよな、これ。ちなみにジャケット写真でペッパーに迫ってる(笑)のはフランク・バトラー(drums)。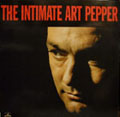 最近になってようやく発売になった(らしい)のが『』『』『』というNYとLAのジャズメンとのセッションを収めた3枚のアルバム。できれば全部聴きたいが、その中でもいいのはLAの共演者との『The Intimate Art Pepper』。クラリネット吹いたりしてますが、まぁ許しましょう。
最近になってようやく発売になった(らしい)のが『』『』『』というNYとLAのジャズメンとのセッションを収めた3枚のアルバム。できれば全部聴きたいが、その中でもいいのはLAの共演者との『The Intimate Art Pepper』。クラリネット吹いたりしてますが、まぁ許しましょう。 延々と「復帰後」のアルバムばかりを並べてきたが、若いころのペッパーはどうなのか、というとこれもなかなか悪くない。良くも悪くもペッパーはなかなか優等生である。『Art Pepper the Early Show』(1952)を聴いてみるとそれが良く分る。この時代にありがちなジャム・セッション風で荒さが(そして録音状態の悪さも)目立つアルバムだが、とにかくペッパーは全編を通して丁寧にそして力強く吹きまくってる。ちなみにこの姉妹版で『Late Show』というのもある。
延々と「復帰後」のアルバムばかりを並べてきたが、若いころのペッパーはどうなのか、というとこれもなかなか悪くない。良くも悪くもペッパーはなかなか優等生である。『Art Pepper the Early Show』(1952)を聴いてみるとそれが良く分る。この時代にありがちなジャム・セッション風で荒さが(そして録音状態の悪さも)目立つアルバムだが、とにかくペッパーは全編を通して丁寧にそして力強く吹きまくってる。ちなみにこの姉妹版で『Late Show』というのもある。ペッパーは演奏が丁寧だったことに加えてかなり完璧主義者だったようで、スタジオでのレコードの吹き込みに際しては20〜30テイクまでやってようやくOKを出すなんてこともしばしばあったらしい。ほとんどリハの続きみたいなテイクで済ませてしまうマイルスに爪の垢でも煎じて飲ませてやりたいくらいである(どちらも死んでるのでもはや飲ませるのは不可能だが)。まぁ、テイク数を増やせばそれだけいい演奏になるかというとそうとも限らないのがジャズのいいところでもあり、恐いところでもある。
最近のジャズミュージシャンたちはヤクもやらないし、きちんとした家に住んで、レコード会社と契約を結んでコンスタントにアルバムを作り、よく言えばとても社会的に真っ当な生き方をしてる。しかし、悪く言えば商業主義にどっぷり漬かって工業製品みたいにレコードを生産しているだけになってしまった。前に取り上げたチェット・ベイカーにしろ、このアート・ペッパーにしろ、いかにもジャズメンらしい壊れた人生を歩んできた世代の最後の生き残りといってよい。でもアート・ペッパーは最期に一花咲かせることができて(とくに日本ではとても人気を得た)本人もすごく喜んでいたそうである。よかったですね。